皆様、お葉っぴー( *´艸`)お世話になっております。とも葉くんです
前回の記事で「地域包括ケアシステム」という言葉を少しご紹介しました
今回はその仕組みを深掘りし、「4つの助」 を中心に、私たちの暮らしにどう関係しているかを見ていきましょう
🏠 地域包括ケアシステムの基本
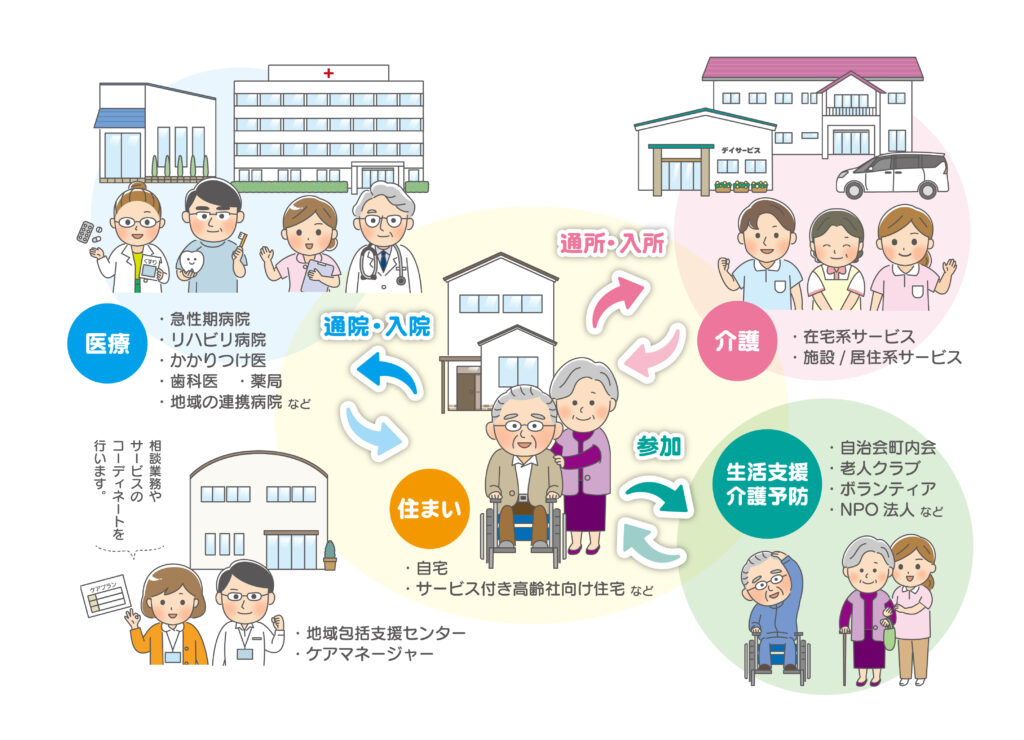
地域包括ケアシステムとは、要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられる ように、地域全体で支え合う仕組みです
構成するのは
✅ 住まい
✅ 医療
✅ 介護
✅ 予防
✅ 生活支援
👉 これらが相互に関わり、一体的に提供されることを目指しています
🌱 植木鉢で考える「地域包括ケアシステム」
地域包括ケアシステムは「難しい制度の話」と思われがちですが、実は身近な植木鉢にたとえて考えると、とてもわかりやすくなります

🥣 皿=本人・家族の心構え
一番下にある皿は、本人の選択と心構え、そして家族の気持ちの持ち方を表しています
地域で暮らし続けるための“基礎”であり、どんな支え合いもここから始まります
🏡 植木鉢=住まい
その上にある植木鉢は、生活の基盤となる「住まい」です
安心して暮らせる住まいがあるからこそ、日々の生活が成り立ちます
🌱 土=介護予防・生活支援
植木鉢に入っている土は、介護予防や生活支援
体操やフレイル予防、買い物支援や見守りといった「暮らしを支える工夫」が、住まいの中での生活を豊かにします
🍃 葉=専門的なサービス
植木鉢から伸びる葉っぱは、専門職によるサービスです
- 医療・看護
- 介護・リハビリテーション
- 保健・福祉
これらの専門的な支援があることで、暮らしの安心が守られます
植木鉢図が示すのは、どの要素も欠かせず、全体がつながり合ってはじめて「その人らしい暮らし」が続くということです
👉 そして大切なのは、皿に描かれた「本人の選択と心構え」
つまり、制度やサービスだけでなく、自分や家族の思いが生活を支える基礎になっているのです
🌱 「4つの助」で考える支え合い
暮らしを守る考え方として大切なのが 「4つの助」 です
①自助:「自分の健康は自分で守る」
②互助:「支える側にも支えられる側にもなれる=お互い様の関係」
③共助:「地域や仕組みを通じた支え合い」
④公助:「国や自治体による最後の砦」
① 自助(じじょ)✨
自分でできることを大切に
- 健康診断を受ける
- 運動や食事で体調管理
- 趣味や学びで心の元気を維持
💡 「自分の健康は自分で守る」 ことが基盤になります
② 互助(ごじょ)🤝
「お互いさま」の関係です
- ご近所に声をかける
- 買い物やゴミ出しを手伝う
- サークル活動や地域サロンに参加
💡 支える側にも支えられる側にもなれるのが互助。つながりが安心をつくります
③ 共助(きょうじょ)🏘️
地域や仕組みを通じた支え合いです
- 介護保険や医療保険のサービス
- NPOや社会福祉協議会の活動
- 町内会やボランティア団体
💡 互助では難しい課題を、仕組みで支える力
④ 公助(こうじょ)🛡️
国や自治体による最後の砦
- 生活保護
- 高額医療費制度
- 虐待・DVへの介入
💡 命や暮らしを守るための“社会全体の支え”です
🎯 バランスが大事
「4つの助」は、どれか一つに頼るのではなく、自助を土台に、互助・共助・公助が重なり合うことで成り立ちます
🌱 一人ひとりの小さな行動が、地域の安心を育てます
✅ 今日からできる「小さな支え合い」3つ
ちょっとした行動でも地域を支える一歩になります
1️⃣ あいさつや声かけを習慣にする 😊
→ つながりの芽を育てます。
2️⃣ 地域の活動に一歩参加してみる 👋
→ 自分も楽しみながら支え合いに関われます
3️⃣ 自分の健康を意識して行動する 🍎
→ 自助を大切にすることが、巡り巡って地域の力に
地域包括ケアシステムの根底にある「4つの助」は、制度だけでなく日常の暮らしに根づく考え方です。🌱 一人ひとりが無理なくできる支え合いを積み重ねることが、安心して暮らせる地域をつくります
👉 あなたも今日から、小さな支え合いを始めてみませんか?
🎥 もっと知りたい方へ
地域包括ケアシステムについては、YouTubeでもわかりやすい動画が紹介されています。
👉 興味のある方はぜひ
出典:埼玉県公式YouTubeチャンネル「地域包括ケアシステムについて」
(YouTube埋め込み動画はこちらからご覧いただけます)
🎨 使用イラスト
- アイキャッチ画像:イラストAC(https://www.ac-illust.com/)より
- 植木鉢図:地域包括ケアシステム|厚生労働省

次回の記事もご閲覧よろしくお願いいたします


