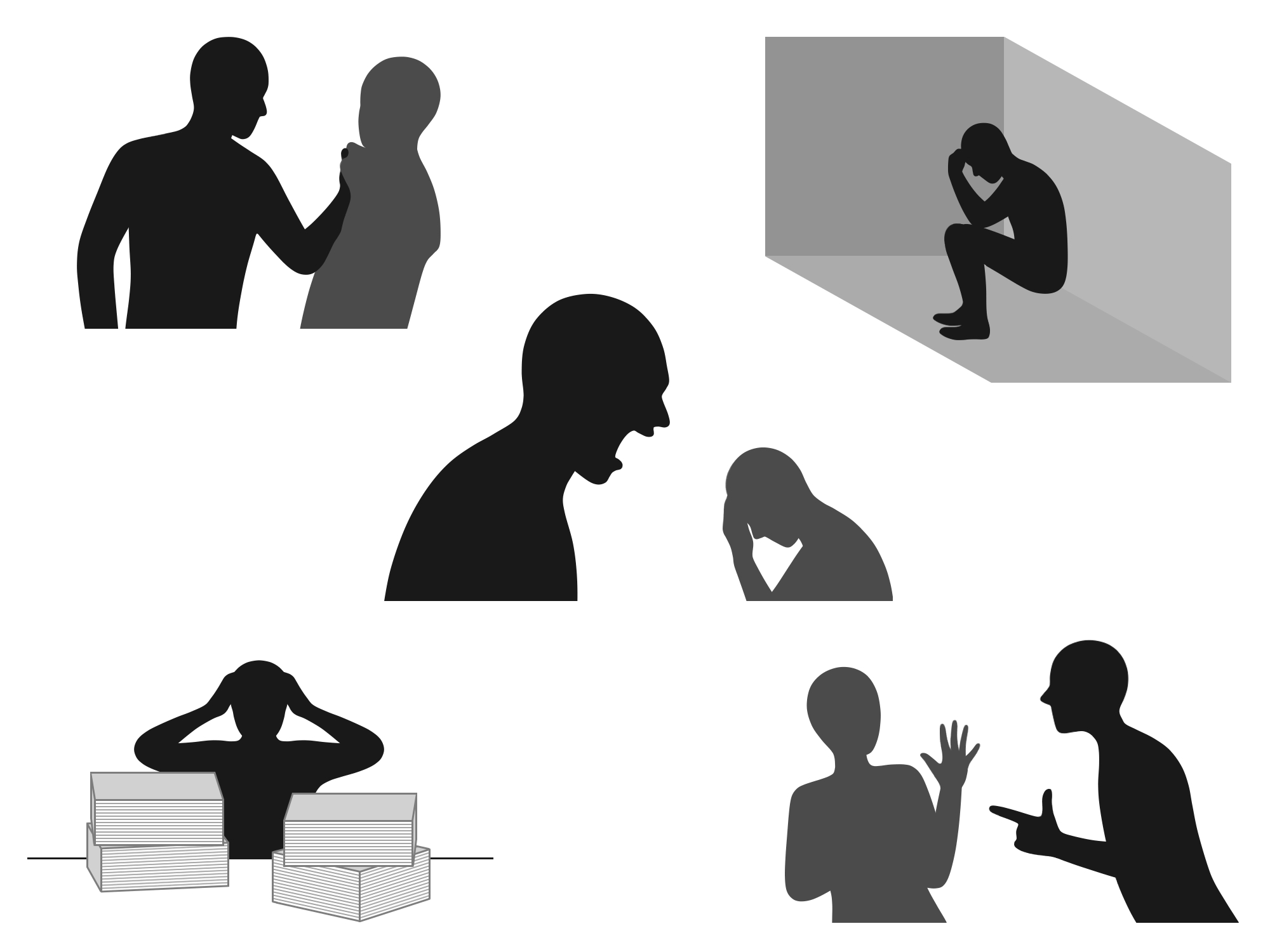〜働くうえでの正しい批判と伝え方〜
👣 世はまさにハラスメント時代である
皆さま、お葉っぴー( *´艸`)とも葉くんです🍃
最近は「なんでもハラスメント」と言われる時代になりましたね
ちょっとした注意や意見交換までも「ハラスメントじゃない?」と受け取られることがあり 息苦しさを感じる職員もいるかもしれません
💬 職員の声:
「改善のために言っただけなのに、“ハラスメント”って言われた…」
ですが一方で、伝え方を誤ると本当に「攻撃的」「不適切」と受け止められ 職場環境を壊してしまうこともあります
本日はそんな「ハラスメント」について、身近な事例や法律、そして介護カテゴリにちなんで 介護現場での注意点を交えながらご紹介いたします
🔍 批判とハラスメントの違い
- 批判(建設的な指摘)
→ 事実に基づき、業務改善を目的として伝えるもの - ハラスメント(不適切な言動)
→ 事実確認を欠き、繰り返し否定し、相手に心理的負担を与えるもの
📌 例
- ✅ 「報告書の提出が遅れているので、次回は期限を守りましょう」
- 🚫 「一度もまともに出したことがない」
🌀 誤解しやすい背景
介護施設のように多職種が連携する現場では、それぞれが担う役割や優先順位が異なります
例えば、介護施設の現場では職種ごとに重視する視点が異なります
🩺 看護職
バイタルサイン管理・服薬・急変対応などを中心に、医療的な安全の確保を最優先
🤝 介護職
食事・排泄・入浴・移動など日常生活動作を支援、生活全般の継続性と安定を重視
・生活リズムや本人らしさを尊重
・業務記録やケアプランの整合性などマネジメント的役割
・書類の見直しや業務の棚卸しも重要
🏃 リハビリ職
ADL・IADLの改善や社会的活動への参加を支援し、「できることを増やす」活動参加支援を重視
・介護職の生活支援と重なる部分が多い
・評価や訓練計画を通じて科学的・計画的にマネジメントするのが特徴
ポイント
視点や役割が違うため、相手の業務を十分理解せずに「やっていない」「できていない」と断定すると、事実とのずれから摩擦やハラスメントに近い状況を生みます
⚠️ 境界線があいまいになる場面
介護施設では、次のようなシーンも良く見受けられます
- 委員会や会議で「特定の部署を断定的に名指しする」
- 掲示板で個人名を出して否定的に書く
- 申し送りで同じことを繰り返し強い口調で言う
❗ 特に「特定の部署を名指しする」ことは要注意。事実確認が不十分なまま名指しをすると 部署全体の信用失墜・士気低下・部署間の関係悪化につながります
🗣️ 言い方を間違えるとどうなる?
🚨 「一度もやっていない」「また同じことをしている」
→ 否定の色合いが強く、繰り返されると「攻撃」と受け止められます
その結果…
- モチベーション低下
- 「自分たちだけ責められている」という不信感
- 部署間の協力関係の悪化
- ハラスメント相談や外部通報
🌱 建設的に伝える工夫
📌 言葉の工夫で「攻撃」から「改善」へ
- 事実に基づく:「先月の報告件数が少ないようです」
- 改善策を添える:「提出方法を一度一緒に確認しましょう」
- 責任を仕組みに向ける:「回覧の流れに抜けがあったかもしれません」
- 場を選ぶ:公の場で大勢の前に指摘するのではなく、個別に伝えるのが原則 公の場では「さらし者にされた」と感じやすく、ハラスメントに近づく危険があります ただし、個別であっても伝え方次第でハラスメントと受け止められることもあります。
- 断定的で強い口調
- 責めるような表現
- 繰り返し同じ内容を言い続ける
こうした要素が重なると「個別注意=ハラスメント」となりかねません
また、指摘する側の普段の立ち振る舞い(挨拶や関わり方)や、相手との信頼関係の有無によっても受け取り方は大きく変わります。そのため、日頃からの接し方を見直すこと自体が、ハラスメント防止の一つの術となります
📋 よくあるNG表現とOK表現
| シーン | 🚫 NG表現 | ✅ OK表現 |
|---|---|---|
| 報告の指摘 | 「一度も出していないですよね?」 | 「最近の件数が少ないので、一緒に確認しましょう」 |
| 申し送り | 「またやってないんですか?」 | 「今日の対応で抜けがあったので、次回は注意していきましょう」 |
| 掲示板 | 「○○さんは対応が遅い」 | 「対応が遅れるケースがあるので、連絡の工夫を考えましょう」 |
| 会議での指摘 | 「いつもサボっている」 | 「業務量に差があるので、分担の見直しを検討しませんか?」 |
| 日常の声かけ | (無視) | 「今は対応中だけど、後で話そうね」と一言添える |
🚨 カスタマーハラスメントにも注意
介護現場では、職員同士だけでなく 利用者やご家族からの過度な要求 による 「カスタマーハラスメント」も課題です
💬 利用者家族の声(NG例):
「お金を払っているんだから、何でもしてもらわないと!」
👉 サービスには限界があります
- 強要や責め立ては職員の尊厳を傷つけます
- 職員も人間であり、無理な要求は負担になります
介護施設は“お金を払えば何でもできる場”ではなく、互いの尊重の上で成り立つ生活の場 であることを忘れてはいけません
さらに背景には、人材不足の深刻化もあります
人員が限られる中で過度な要求が繰り返されると、職員の心理的負担は大きく、離職やサービス低下にも直結してしまいます
➡ この点については、以前のブログ記事でも「人材不足の深刻化」について詳しく取り上げています。あわせてご覧ください
⚖️ ハラスメントに関する法律
日本には「ハラスメント防止法」という単独の法律はありません
しかし、複数の法律やガイドラインで、職場でのハラスメント防止が義務づけられています
1. 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
- 2019年改正で事業主に「職場のパワハラ防止措置」が義務化
- 大企業は2020年、中小企業は2022年から適用
- 介護施設も対象であり
- 防止方針の明示
- 相談窓口の設置
- 迅速・適切な事後対応
が求められます
2. 男女雇用機会均等法
- セクシュアルハラスメントやマタニティ・ハラスメントの防止を規定
- 妊娠・出産・育児休業等を理由にした嫌がらせも対象
3. 労働契約法・民法
- 職場でのハラスメントは「安全配慮義務違反」として損害賠償請求につながる可能性
4. カスタマーハラスメント(厚労省ガイドライン)
- 直接の法律はないが、厚労省が「事業主は対応努力をすべき」と明示
- 利用者・家族からの過度な要求や攻撃的言動も、施設として対応方針を定めることが重要
✅ まとめ
「なんでもハラスメント」と言われがちな時代だからこそ
正しい批判=改善のための建設的な指摘 が必要です
- 事実確認に基づいているか
- 繰り返し性がないか
- 改善策を含んでいるか
- 特定の個人や部署を名指ししていないか
- 過度な要求や責め立てになっていないか
💡 この5点を意識すれば、相手に伝わるのは「攻撃」ではなく「改善」です
❓ あなたの職場ではどうでしょうか?
委員会・申し送り・掲示板、そしてご家族とのやりとり
それは“改善につながる批判”になっていますか?
それとも“ハラスメント”に近づいていませんか?
🎥 東京都公式動画のご紹介
ハラスメントは「大声や威圧的な態度」などの行為によっても発生する可能性があります
東京都が制作した公式動画では、その危険性について分かりやすく解説されています
職場研修や自己学習の参考にぜひご覧ください
※本動画は東京都が公開した公式動画を埋め込んでいます。編集や再配布は行っていません。
📚 参考リンク(公式情報)
🔗 厚生労働省・公式関連ページ
職場におけるハラスメント防止のために
職場におけるハラスメント(PDF)
📖 基礎知識・法的根拠
パワーハラスメントの定義(あかるい職場応援団)
ハラスメントに関する法律と防止措置
🆘 相談・実務向け
相談窓口のご案内(労働局・あかるい職場応援団)
ハラスメント関係資料ダウンロードコーナー
🛠 実務で使える資料
パワーハラスメント対策について(地方労働局)
ハラスメント防止のために ~なぜ対策が必要か~(PDF)
パワハラ対策導入マニュアル(PDF)
⚖️ 裁判例・事例
裁判例を見てみよう(あかるい職場応援団)
🎨 使用イラスト
- アイキャッチ画像:イラストAC(https://www.ac-illust.com/)より

次回の記事もご閲覧よろしくお願いいたします